大学入学共通テスト(国語) 過去問
令和5年度(2023年度)本試験
問8 (<旧課程>第1問(評論) 問8)
問題文
次の【文章Ⅰ】は、正岡子規(まさおかしき)の書斎にあったガラス障子と建築家ル・コルビュジエの建築物における窓について考察したものである。また、【文章Ⅱ】は、ル・コルビュジエの窓について【文章Ⅰ】とは別の観点から考察したものである。どちらの文章にもル・コルビュジエ著『小さな家』からの引用が含まれている(引用文中の(中略)は原文のままである)。これらを読んで、後の問いに答えよ。なお、設問の都合で表記を一部改めている。
【文章Ⅰ】
寝返りさえ自らままならなかった子規にとっては、室内にさまざまなものを置き、それをながめることが楽しみだった。そして、ガラス障子のむこうに見える庭の植物や空を見ることが慰めだった。味覚のほかは視覚こそが子規の自身の存在を確認する感覚だった。子規は、視覚の人だったともいえる。障子の紙をガラスに入れ替えることで、A 子規は季節や日々の移り変わりを楽しむことができた。
『墨汁一滴』(注1)の3月12日には「不平十ケ条(じっかじょう)」として、「板ガラスの日本で出来ぬ不平」と書いている。この不平を述べている1901(明治34)年、たしかに日本では板ガラスは製造していなかったようだ。石井研堂(注2)の『増訂明治事物起原』には、「(明治)36年、原料も総(すべ)て本邦のものにて、完全なる板硝子(いたがらす)を製出せり。大正3年、欧州大戦の影響、本邦の輸入硝子は其(その)船便を失ふ、是(ここ)に於(おい)て、旭(あさひ)硝子製造会社等の製品が、漸(ようや)く用ひらるることとなり、わが板硝子界は、大発展を遂ぐるに至れり」とある。
これによると板ガラスの製造が日本で始まったのは、1903年ということになる。子規が不平を述べた2年後である。してみれば、虚子(注3)のすすめで子規の書斎(病室)に入れられた「ガラス障子」は、輸入品だったのだろう。高価なものであったと思われる。高価であってもガラス障子にすることで、子規は、庭の植物に季節の移ろいを見ることができ、青空や雨をながめることができるようになった。ほとんど寝たきりで身体を動かすことができなくなり、絶望的な気分の中で自殺することも頭によぎっていた子規。彼の書斎(病室)は、ガラス障子によって「見ることのできる装置(室内)」あるいは「見るための装置(室内)」へと変容したのである。
映画研究者のアン・フリードバーグ(注4)は、『ヴァーチャル・ウインドウ』のアボウトウで、「窓」は「フレーム」であり「スクリーン」でもあるといっている。
窓はフレームであるとともに、プロセニアム〔舞台と客席を区切る額縁状の部分〕でもある。窓の縁〔エッジ〕が、風景を切り取る。窓は外界を二次元の平面へと変える。つまり、窓はスクリーンとなる。窓と同様に、スクリーンは平面であると同時にフレーム ――― 映像〔イメージ〕が投影される反射面であり、視界を制限するフレーム ――― でもある。スクリーンは建築のひとつの構成要素であり、新しいやり方で、壁の通風を演出する。
子規の書斎は、ガラス障子によるプロセニアムがつくられたのであり、それは外界を二次元に変えるスクリーンでありフレームとなったのである。B ガラス障子は「視覚装置」だといえる。
子規の書斎(病室)の障子をガラス障子にすることで、その室内は「視覚装置」となったわけだが、実のところ、外界をながめることのできる「窓」は、視覚装置として、建築・住宅にもっとも重要な要素としてある。
建築家のル・コルビュジエは、いわば視覚装置としての「窓」をきわめて重視していた。そして、彼は窓の構成こそ、建築を決定しているとまで考えていた。したがって、子規の書斎(病室)とは比べものにならないほど、ル・コルビュジエは、視覚装置としての窓の多様性を、デザインつまり表象として実現していった。とはいえ、窓が視覚装置であるという点においては、子規の書斎(病室)のガラス障子といささかもかわることはない。しかし、ル・コルビュジエは、住まいを徹底した視覚装置、まるでカメラのように考えていたという点では、子規のガラス障子のようにおだやかなものではなかった。子規のガラス障子は、フレームではあっても、操作されたフレームではない。他方、C ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった。
ル・コルビュジエは、ブエノス・アイレスでイ行った講演のなかで、「建築の歴史を窓の各時代の推移で示してみよう」といい、また窓によって「建築の性格が決定されてきたのです」と述べている。そして、古代ポンペイの出窓、ロマネスクの窓、ゴシックの窓、さらに19世紀パリの窓から現代の窓のあり方までを歴史的に検討してみせる。そして「窓は採光のためにあり、換気のためではない」とも述べている。こうしたル・コルビュジエの窓についての言説について、アン・フリードバーグは、ル・コルビュジエのいう住宅は「住むための機械」であると同時に、それはまた「見るための機械でもあった」のだと述べている。さらに、ル・コルビュジエは、窓に換気ではなく「視界と採光」を優先したのであり、それは「窓のフレームと窓の形、すなわち「アスペクト比」の変更を引き起こした」と指摘している。ル・コルビュジエは窓を、外界を切り取るフレームだと捉えており、その結果、窓の形、そして「アスペクト比」(ディスプレイの長辺と短辺の比)が変化したというのである。
実際彼は、両親のための家をレマン湖のほとりに建てている。まず、この家は、塀(壁)で囲まれているのだが、これについてル・コルビュジエは、次のように記述している。
囲い壁の存在理由は、北から東にかけて、さらに部分的に南から西にかけて視界を閉ざすためである。四方八方に蔓延する景色というものは圧倒的で、焦点をかき、長い間にはかえって退屈なものになってしまう。このような状況では、もはや「私たち」は風景を「眺める」ことができないのではないだろうか。景色をウ望むには、むしろそれを限定しなければならない。思い切った判断によって選別しなければならないのだ。すなわち、まず壁を建てることによって視界を遮ぎり、つぎに連らなる壁面を要所要所取り払い、そこに水平線の広がりを求めるのである。
引用元:『小さな家 Une petite maison, 1923』 1954年(森田一敏訳、集文社、1980年)
(『小さな家』(注5))
風景を見る「視覚装置」としての窓(開口部)と壁をいかに構成するかが、ル・コルビュジエにとって課題であったことがわかる。
(柏木博(かしわぎひろし)『視覚の生命力 ――― イメージの復権』による)
【文章Ⅱ】
1920年代の最後期を飾る初期の古典的作品サヴォア邸(注6)は、見事なプロポーション(注7)をもつ「横長の窓」を示す。が一方、「横長の窓」を内側から見ると、それは壁をくりぬいた窓であり、その意味は反転する。それは四周を遮る壁体となる。「横長の窓」は、「横長の壁」となって現われる。「横長の窓」は1920年代から1930年代に入ると、「全面ガラスの壁面」へと移行する。スイス館(注8)がこれをよく示している。しかしながらスイス館の屋上庭園の四周は、強固な壁で囲われている。大気は壁で仕切られているのである。
かれは初期につぎのようにいう。「住宅は沈思黙考の場である」。あるいは「人間には自らを消耗する〈仕事の時間〉があり、自らをひき上げて、心のエキンセンに耳を傾ける〈瞑想(めいそう)の時間〉とがある」。
これらの言葉には、いわゆる近代建築の理論においては説明しがたい一つの空間論が現わされている。一方は、いわば光のオウトんじられる世界であり、他方は光の溢(あふ)れる世界である。つまり、前者は内面的な世界に、後者は外的な世界に関わっている。
かれは『小さな家』において「風景」を語る:
省略
ここに語られる「風景」は動かぬ視点をもっている。かれが多くを語った「動く視点」にたいするこの「動かぬ視点」は風景を切り取る。視点と風景は、一つの壁によって隔てられ、そしてつながれる。風景は一点から見られ、眺められる。D 壁がもつ意味は、風景の観照の空間的構造化である。この動かぬ視点theōria(テオリア)(注9)の存在は、かれにおいて即興的なものではない。
かれは、住宅は、沈思黙考、美に関わると述べている。初期に明言されるこの思想は、明らかに動かぬ視点をもっている。その後の展開のなかで、沈思黙考の場をうたう住宅論は、動く視点が強調されるあまり、ル・コルビュジエにおいて影をひそめた感がある。しかしながら、このテーマはル・コルビュジエが後期に手がけた「礼拝堂」や「修道院」(注10)において再度主題化され、深く追求されている。「礼拝堂」や「修道院」は、なによりも沈思黙考、瞑想の場である。つまり、後期のこうした宗教建築を問うことにおいて、動く視点にたいするル・コルビュジエの動かぬ視点の意義が明瞭になる。
(呉谷充利(くれたにみつとし)『ル・コルビュジエと近代絵画 ――― 20世紀モダニズムの道程』による)
(注1)『墨汁一滴』 ――― 正岡子規(1867 ― 1902)が1901年に著した随筆集。
(注2)石井研堂 ――― ジャーナリスト、明治文化研究家(1865―1943)。
(注3)虚子 ――― 高浜虚子(1874―1959)。俳人、小説家。正岡子規に師事した。
(注4)アン・フリードバーグ ――― アメリカの映像メディア研究者(1952―2009)。
(注5)『小さな家』 ――― ル・コルビュジエ(1887―1965)が1954年に著した書物。自身が両親のためにレマン湖のほとりに建てた家について書かれている。
(注6)サヴォア邸 ――― ル・コルビュジエの設計で、パリ郊外に建てられた住宅。
(注7)プロポーション ――― つりあい。均整。
(注8)スイス館 ――― ル・コルビュジエの設計で、パリに建てられた建築物。
(注9)動かぬ視点theōria(テオリア) ――― ギリシア語で、「見ること」「眺めること」の意。
(注10)「礼拝堂」や「修道院」 ――― ロンシャンの礼拝堂とラ・トゥーレット修道院を指す。
下線部C「ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった」とあるが、「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果の説明として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
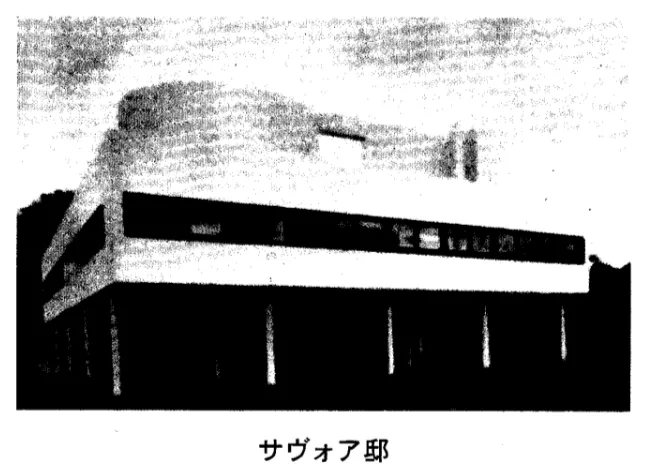
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問8(<旧課程>第1問(評論) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の【文章Ⅰ】は、正岡子規(まさおかしき)の書斎にあったガラス障子と建築家ル・コルビュジエの建築物における窓について考察したものである。また、【文章Ⅱ】は、ル・コルビュジエの窓について【文章Ⅰ】とは別の観点から考察したものである。どちらの文章にもル・コルビュジエ著『小さな家』からの引用が含まれている(引用文中の(中略)は原文のままである)。これらを読んで、後の問いに答えよ。なお、設問の都合で表記を一部改めている。
【文章Ⅰ】
寝返りさえ自らままならなかった子規にとっては、室内にさまざまなものを置き、それをながめることが楽しみだった。そして、ガラス障子のむこうに見える庭の植物や空を見ることが慰めだった。味覚のほかは視覚こそが子規の自身の存在を確認する感覚だった。子規は、視覚の人だったともいえる。障子の紙をガラスに入れ替えることで、A 子規は季節や日々の移り変わりを楽しむことができた。
『墨汁一滴』(注1)の3月12日には「不平十ケ条(じっかじょう)」として、「板ガラスの日本で出来ぬ不平」と書いている。この不平を述べている1901(明治34)年、たしかに日本では板ガラスは製造していなかったようだ。石井研堂(注2)の『増訂明治事物起原』には、「(明治)36年、原料も総(すべ)て本邦のものにて、完全なる板硝子(いたがらす)を製出せり。大正3年、欧州大戦の影響、本邦の輸入硝子は其(その)船便を失ふ、是(ここ)に於(おい)て、旭(あさひ)硝子製造会社等の製品が、漸(ようや)く用ひらるることとなり、わが板硝子界は、大発展を遂ぐるに至れり」とある。
これによると板ガラスの製造が日本で始まったのは、1903年ということになる。子規が不平を述べた2年後である。してみれば、虚子(注3)のすすめで子規の書斎(病室)に入れられた「ガラス障子」は、輸入品だったのだろう。高価なものであったと思われる。高価であってもガラス障子にすることで、子規は、庭の植物に季節の移ろいを見ることができ、青空や雨をながめることができるようになった。ほとんど寝たきりで身体を動かすことができなくなり、絶望的な気分の中で自殺することも頭によぎっていた子規。彼の書斎(病室)は、ガラス障子によって「見ることのできる装置(室内)」あるいは「見るための装置(室内)」へと変容したのである。
映画研究者のアン・フリードバーグ(注4)は、『ヴァーチャル・ウインドウ』のアボウトウで、「窓」は「フレーム」であり「スクリーン」でもあるといっている。
窓はフレームであるとともに、プロセニアム〔舞台と客席を区切る額縁状の部分〕でもある。窓の縁〔エッジ〕が、風景を切り取る。窓は外界を二次元の平面へと変える。つまり、窓はスクリーンとなる。窓と同様に、スクリーンは平面であると同時にフレーム ――― 映像〔イメージ〕が投影される反射面であり、視界を制限するフレーム ――― でもある。スクリーンは建築のひとつの構成要素であり、新しいやり方で、壁の通風を演出する。
子規の書斎は、ガラス障子によるプロセニアムがつくられたのであり、それは外界を二次元に変えるスクリーンでありフレームとなったのである。B ガラス障子は「視覚装置」だといえる。
子規の書斎(病室)の障子をガラス障子にすることで、その室内は「視覚装置」となったわけだが、実のところ、外界をながめることのできる「窓」は、視覚装置として、建築・住宅にもっとも重要な要素としてある。
建築家のル・コルビュジエは、いわば視覚装置としての「窓」をきわめて重視していた。そして、彼は窓の構成こそ、建築を決定しているとまで考えていた。したがって、子規の書斎(病室)とは比べものにならないほど、ル・コルビュジエは、視覚装置としての窓の多様性を、デザインつまり表象として実現していった。とはいえ、窓が視覚装置であるという点においては、子規の書斎(病室)のガラス障子といささかもかわることはない。しかし、ル・コルビュジエは、住まいを徹底した視覚装置、まるでカメラのように考えていたという点では、子規のガラス障子のようにおだやかなものではなかった。子規のガラス障子は、フレームではあっても、操作されたフレームではない。他方、C ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった。
ル・コルビュジエは、ブエノス・アイレスでイ行った講演のなかで、「建築の歴史を窓の各時代の推移で示してみよう」といい、また窓によって「建築の性格が決定されてきたのです」と述べている。そして、古代ポンペイの出窓、ロマネスクの窓、ゴシックの窓、さらに19世紀パリの窓から現代の窓のあり方までを歴史的に検討してみせる。そして「窓は採光のためにあり、換気のためではない」とも述べている。こうしたル・コルビュジエの窓についての言説について、アン・フリードバーグは、ル・コルビュジエのいう住宅は「住むための機械」であると同時に、それはまた「見るための機械でもあった」のだと述べている。さらに、ル・コルビュジエは、窓に換気ではなく「視界と採光」を優先したのであり、それは「窓のフレームと窓の形、すなわち「アスペクト比」の変更を引き起こした」と指摘している。ル・コルビュジエは窓を、外界を切り取るフレームだと捉えており、その結果、窓の形、そして「アスペクト比」(ディスプレイの長辺と短辺の比)が変化したというのである。
実際彼は、両親のための家をレマン湖のほとりに建てている。まず、この家は、塀(壁)で囲まれているのだが、これについてル・コルビュジエは、次のように記述している。
囲い壁の存在理由は、北から東にかけて、さらに部分的に南から西にかけて視界を閉ざすためである。四方八方に蔓延する景色というものは圧倒的で、焦点をかき、長い間にはかえって退屈なものになってしまう。このような状況では、もはや「私たち」は風景を「眺める」ことができないのではないだろうか。景色をウ望むには、むしろそれを限定しなければならない。思い切った判断によって選別しなければならないのだ。すなわち、まず壁を建てることによって視界を遮ぎり、つぎに連らなる壁面を要所要所取り払い、そこに水平線の広がりを求めるのである。
引用元:『小さな家 Une petite maison, 1923』 1954年(森田一敏訳、集文社、1980年)
(『小さな家』(注5))
風景を見る「視覚装置」としての窓(開口部)と壁をいかに構成するかが、ル・コルビュジエにとって課題であったことがわかる。
(柏木博(かしわぎひろし)『視覚の生命力 ――― イメージの復権』による)
【文章Ⅱ】
1920年代の最後期を飾る初期の古典的作品サヴォア邸(注6)は、見事なプロポーション(注7)をもつ「横長の窓」を示す。が一方、「横長の窓」を内側から見ると、それは壁をくりぬいた窓であり、その意味は反転する。それは四周を遮る壁体となる。「横長の窓」は、「横長の壁」となって現われる。「横長の窓」は1920年代から1930年代に入ると、「全面ガラスの壁面」へと移行する。スイス館(注8)がこれをよく示している。しかしながらスイス館の屋上庭園の四周は、強固な壁で囲われている。大気は壁で仕切られているのである。
かれは初期につぎのようにいう。「住宅は沈思黙考の場である」。あるいは「人間には自らを消耗する〈仕事の時間〉があり、自らをひき上げて、心のエキンセンに耳を傾ける〈瞑想(めいそう)の時間〉とがある」。
これらの言葉には、いわゆる近代建築の理論においては説明しがたい一つの空間論が現わされている。一方は、いわば光のオウトんじられる世界であり、他方は光の溢(あふ)れる世界である。つまり、前者は内面的な世界に、後者は外的な世界に関わっている。
かれは『小さな家』において「風景」を語る:
省略
ここに語られる「風景」は動かぬ視点をもっている。かれが多くを語った「動く視点」にたいするこの「動かぬ視点」は風景を切り取る。視点と風景は、一つの壁によって隔てられ、そしてつながれる。風景は一点から見られ、眺められる。D 壁がもつ意味は、風景の観照の空間的構造化である。この動かぬ視点theōria(テオリア)(注9)の存在は、かれにおいて即興的なものではない。
かれは、住宅は、沈思黙考、美に関わると述べている。初期に明言されるこの思想は、明らかに動かぬ視点をもっている。その後の展開のなかで、沈思黙考の場をうたう住宅論は、動く視点が強調されるあまり、ル・コルビュジエにおいて影をひそめた感がある。しかしながら、このテーマはル・コルビュジエが後期に手がけた「礼拝堂」や「修道院」(注10)において再度主題化され、深く追求されている。「礼拝堂」や「修道院」は、なによりも沈思黙考、瞑想の場である。つまり、後期のこうした宗教建築を問うことにおいて、動く視点にたいするル・コルビュジエの動かぬ視点の意義が明瞭になる。
(呉谷充利(くれたにみつとし)『ル・コルビュジエと近代絵画 ――― 20世紀モダニズムの道程』による)
(注1)『墨汁一滴』 ――― 正岡子規(1867 ― 1902)が1901年に著した随筆集。
(注2)石井研堂 ――― ジャーナリスト、明治文化研究家(1865―1943)。
(注3)虚子 ――― 高浜虚子(1874―1959)。俳人、小説家。正岡子規に師事した。
(注4)アン・フリードバーグ ――― アメリカの映像メディア研究者(1952―2009)。
(注5)『小さな家』 ――― ル・コルビュジエ(1887―1965)が1954年に著した書物。自身が両親のためにレマン湖のほとりに建てた家について書かれている。
(注6)サヴォア邸 ――― ル・コルビュジエの設計で、パリ郊外に建てられた住宅。
(注7)プロポーション ――― つりあい。均整。
(注8)スイス館 ――― ル・コルビュジエの設計で、パリに建てられた建築物。
(注9)動かぬ視点theōria(テオリア) ――― ギリシア語で、「見ること」「眺めること」の意。
(注10)「礼拝堂」や「修道院」 ――― ロンシャンの礼拝堂とラ・トゥーレット修道院を指す。
下線部C「ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった」とあるが、「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果の説明として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
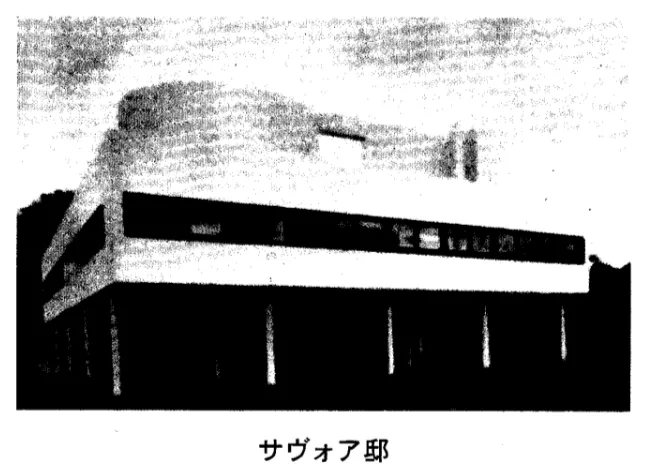
- ル・コルビュジエの窓は、外界に焦点を合わせるカメラの役割を果たすものであり、壁を枠として視界を制御することで風景がより美しく見えるようになる。
- ル・コルビュジエの窓は、居住性を向上させる機能を持つものであり、採光を重視することで囲い壁に遮られた空間の生活環境が快適なものになる。
- ル・コルビュジエの窓は、アスペクト比の変更を目的としたものであり、外界を意図的に切り取ることで室外の景色が水平に広がって見えるようになる。
- ル・コルビュジエの窓は、居住者に対する視覚的な効果に配慮したものであり、囲い壁を効率よく配置することで風景への没入が可能になる。
- ル・コルビュジエの窓は、換気よりも視覚を優先したものであり、視点が定まりにくい風景に限定を施すことでかえって広がりが認識されるようになる。
正解!素晴らしいです
残念...

この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解答するポイントは以下の3点です。
①この問いは何を読み取ればいいのか。
②「「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果の説明」を文章中から抽出すること。
③最も適当なもの=「筆者の意図に沿っているもの」を選ぶこと。
窓を枠として使用するのであり、「壁を枠として視界を制御」しているのではありませんので、不適当です。
「採光を重視する」との表現はありますが、それが「居住性を向上させる機能を持つ」という記述は本文中にないため、不適当です。
「ル・コルビュジエの窓は、アスペクト比の変更を目的としたもの」という記述は本文中にないため、不適当です。
窓を枠として使用するのであり、「囲い壁」を利用したものではありませんので、不適当です。
換気よりも視覚を優先したという趣旨は本文にて説明されているとおりです。
フレームを用いて外の景色の範囲を限定する旨の文章もありましたので、こちらが正解です。
最初に提示したとおり、解答するポイントは以下の3点です。
①この問いは何を読み取ればいいのか。
→選択肢はいずれも「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果について説明しています。
ですので、本文中から「特徴」「効果」が書かれているところを探し出し、文意と合っているか確認していけば良いと分かります。
②「「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果の説明」を文章中から抽出すること。
→傍線部Cを含む段落を見ると、窓の持つ視覚装置としての役割自体は同じですが、子規の書斎は『操作されたものではない』=自然とフレーム機能を持ちその役割を果たしたとしています。
他方でル・コルビュジエは、『住まいを徹底した視覚装置、まるでカメラのように考え』自身の強固な意図の上で緻密な計算の基にフレーム化させたと書かれています。
また、『窓に換気ではなく「視界と採光」を優先したのであり、それは「窓のフレームと窓の形の変更を引き起こした』とあるように、従来の窓の形を変更してまでも視覚装置であることを優先させたと分かります。
③最も適当なもの=「筆者の意図に沿っているもの」を選ぶこと。
→選択肢を選定する際、勝手な行間の読み過ぎが邪魔になることが多々発生します。
・選択肢の文章と問題の本文が示す言葉にずれがないか。
・書かれていない背景を作問者が拡大解釈のもとで示していないか。
上記に注意し、選択肢のおかしいと思った箇所に印をつけると検討しやすく、見直しもやりやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
まず、大前提として「ル・コルビュジエの窓は、確信を持ってつくられたフレームであった」と表現するからには、筆者はル・コルビュジエの窓は普通の家屋の窓と違った役割を持っていると考えているはずです。
それを踏まえた上で本文を読むと、ル・コルビュジエの窓について以下の情報が得られます。
・採光のためにあり、換気のためではない。
・外界を切り取るフレームとしての役割を意識した上でアスペクト比が設定されている。
・(『小さな家』の引用より)景色を「望む」には、四方八方に広がる外の風景を壁や窓で限定する必要がある。
・ゆえに、風景を見る「視覚装置」としての窓と壁の構成がル・コルビュジエにとっては重要だった。
これらの情報をふまえた上で、まずは自分なりに「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果に関する説明文を作ってみましょう。
それから選択肢を一通り読み、自分の考えに最も近いものを正解候補として検証していきます。
ただし、ここで即決するのではなく、除外した候補についても本文と比較して根拠を求めましょう。
「ル・コルビュジエは、住まいを徹底した視覚装置、まるでカメラのように考えていた」という記述はありますが、文章の主旨によると、これは窓だけでなく「窓と壁」の組み合わせによって実現するものです。
さらに、壁と窓で作られた「選別された風景」がもたらすものは「水平線の広がり」であり、「風景がより美しく見えるようになる」では具体性に欠けているため、このことからも最も適当な選択肢とは言えません。
本文では、ル・コルビュジエの窓は換気ではなく「視界と採光」を優先したものとして論じられているため、「居住性を向上させる機能を持つもの」という表現が本文と相違しています。
したがって、この選択肢は誤りです。
ル・コルビュジエの窓は、外界を切り取る「フレーム」の役割を追求した結果としてアスペクト比に変化をきたすことになったのであり、アスペクト比の変更が元々の目的ではありません。
したがって、この選択肢は誤りです。
壁と窓によって外界の風景を限定することで景色を「望む」ことができるとは述べられていますが、「風景への没入が可能」とまでは書かれていないため、この選択肢は誤りです。
「換気よりも視覚を優先したもの」「視点が定まりにくい風景に限定を施すことでかえって広がりが認識される」ともに本文の主旨を正しく反映した説明となっているため、この選択肢が正解です。
今回は以下の方法で正解を導きました。
①本文から重要と思われる情報を拾い、自分の頭の中で正解の文章をイメージする。
②各選択肢を見る。
③最初に自分が考えたものに最も近い選択肢を押さえる。
④念のため、正解候補から外れる選択肢を消し込んでいく(本文をもとに根拠を得ながら)。
⑤最も正しいと思われる選択肢の判断根拠を本文から見つけ、答えを確定する。
この方法を用いることで、選択肢だけを読んで迷ってしまう事態を防ぐことができます。
なお、参考まで『小さな家』で語られているレマン湖畔の家の画像を検索してみるとル・コルビュジエの建築に対する理解が深まります。
気になった事はその都度調べる行動の積み重ねが、試験本番やその先の人生で効果を発揮します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
「ル・コルビュジエの窓」の特徴と効果について最も適切に書かれているものは、「ル・コルビュジエの窓は、換気よりも視覚を優先したものであり、視点が定まりにくい風景に限定を施すことでかえって広がりが認識されるようになる。」という選択肢となります。
「ル・コルビュジエの窓」について書かれている部分をカギ括弧でくくったり、特徴と効果に該当する部分に傍線を引いたりすると、回答しやすくなります。
それでは各選択肢を見ていきましょう。
前半が誤りのため不適当です。
ル・コルビュジエは家自体を、外界を切り取り、室内を「外を見るための視覚装置」にする意味として「カメラ」だとは考えていますが、「外界に焦点を合わせる」と考えてはいません。
「カメラ」という表現は、あくまでも窓を設けることで室内がどのように変容するかについて言及されたものです。
後半については本文と矛盾しません。
全体においてほぼ誤りのため、不適当です。
ル・コルビュジエの窓に「居住性を向上させる機能」はありません。
「換気よりも採光と視覚」「デザイン性」を重視したことからも、住みよい家ではなく美しさを追求したことがわかります。
「採光を重視」の部分だけは合っています。
因果関係が逆のため不適当です。
「アスペクト比の変更を目的」としてはいません。
「外界を意図的に切り取」った結果として、「アスペクト比の変更」が起こっています。
後半が誤りのため不適当です。
前半は本文と大きく矛盾しません。
後半の「囲い壁を効率よく配置」「風景への没入」が正しいといえない部分です。
「窓(開口部)と壁をいかに構成するかが、ル・コルビュジエにとって課題であった」とあるように、ル・コルビュジエは「壁を効率よく配置」すれば視覚的効果を得られる」とは考えていません。
窓と壁のバランスを考えています。
また、「風景への没入」はどこにも記載がなく、正しいとも誤りともいえない部分です。
これらを総合して、不適当となります。
適当です。
前半が正しいのはすぐにわかりますが、後半については判断しづらい部分でしょう。
「限定を施すことでかえって広がりが認識される」はアスペクト比や水平方向へ長い窓の説明を言い換えたもののため、適当です。
「視点が定まりにくい風景」については記載がないため迷うでしょうが、他の選択肢が明らかな誤りを含んでいるため、この選択肢が最も適当だといえます。
何度も言い換えを含んでいる本文を、さらに選択肢でも言い換えられると困惑するでしょう。
文章中で同じ意味として使われている単語は丸で囲み線でつなぐ、などで練習していくと、言い換えや遠回しな表現に慣れていきます。
過去問を数こなして文章に慣れていきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧
次の問題(問9)へ